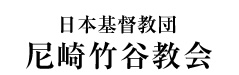「聖 書」
ちょうどそのとき、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。「そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い者だったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。
また、シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。
そして、イエスは次のたとえを話された。「ある人がぶどう園にいちじくの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで、園丁に言った。『もう三年もの間、このいちじくの木に実を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ、土地をふさがせておくのか。』園丁は答えた。『御主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもだめなら、切り倒してください。』」
(ルカによる福音書 13章1~9節)
「悔い改めの実」
本日の御言葉は「悔い改めの招き」と題されて、伝統的に四旬節第三主日に読まれてきた祝福のテキストです。冒頭句にて、「ちょうどそのとき」と始まります。「そのとき」とは、主イエスが群衆に、また弟子たちに説教をしていた時であり、直前には「今の時を見分ける」話をしていた時でした。「その時」ある人々が来て、「今の時」の事件の話を主イエスにします。主は彼らの心の中を見抜かれました。又、群衆の心の中にあることをも察しせられ、他の事故のことも語られた後に「あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる」と言われました。これは不幸な死を遂げた者を滅びと勿論言われたわけではありません。人々が不幸な死を遂げる者に対して、心無い言葉「罪深い者だったのでは」と語る無慈悲さと、自己保全の立場に自らを置き、人ごとのことばかりを語り、自らの罪深さに向き合わない「彼らの滅びの姿」を指摘したのです。人は、その死に方にかかわらずに、「悔い改め」なくしては、すべての者は滅ぶ(永遠の死)定めなのです。ですから主は「今の時」を語られました。今は救いの時なのだと語られたのです。主は、「そして」「実のならないいちじくの木」のたとえを語られました。このたとえはユダヤ人には馴染みのあるものでした。「ぶどう園の実のならないいちじくの木は良い土地で育てたので、どこに植え替えても実はならない」の意味です。ぶどう園もいちじくの木もイスラエルを象徴しています。イスラエルは神から愛され、良くしてもらいました。しかし、彼らは「悔い改めの実」を結びませんでした。そこに主イエスが彼らの前に来られました。三年間の公生涯にて、福音を告げられ、福音を具体化し、神のしるしを見せられました。しかし彼らは悔い改めませんでした。他人事であったのです。(主)園丁は切り倒せと語る主人に対して「御主人様(神)、今年もこのままにしておいてください」と執り成しをします。園丁は特別な世話をすることで主人に猶予をもらいました。「特別な世話」とは「十字架の贖い」のことです。それでも実を結ばなかったら神(主人)が裁きを下して下さいとも主は言われています。主は今も「執り成しの愛」を続けておられます。「今は恵みの時、救いの日です。」(コリント二6:2)は、今も主の執り成しが、あり続けている恵みのことです。私共は、主の愛に応え「悔い改めの実」を結びたいのです。それは神の平安を得ることです。