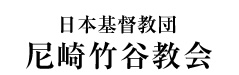「聖 書」
徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と不平を言い出した。そこで、イエスは次のたとえを話された。…
イエスは言われた。「ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言った。それで、父親は財産を二人に分けてやった。何日もたたないうちに、下の息子は全部を金に換えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。…ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。』しかし、父親は僕たちに言った。『急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』そして、祝宴を始めた。
(ルカによる福音書15章1~3,11~32節)
「罪人たちを迎えて」
本日の有名な御言葉である「放蕩息子」をコンテキスト(文脈)に沿いつつ、解き明かしを致します。主イエスの福音の具体(言葉と業)が世に広がり、人々の関心が高まっています。そこに「徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た」と御言葉は冒頭で語ります。そこには他の者もいました。ファリサイ派の人々や律法学者たちです。彼らは主が罪人と交わる姿を見て、「この人は罪人たちを迎えて、食事までしている」と不平を言いました。彼らは救いを求める者を「罪人」(ハマルトース)と断罪しているのです。「迎えて」(プロスデコーマイ)は「受け入れる、引き受ける」の意です。彼らにとって「食事」は「聖卓」であり、礼拝です。ですから主イエスの振る舞いは彼らにとって、「聖卓を汚す行為」であり、「不遜な振る舞いを為す輩は何者か?何ほどの者とは思えないが」という苛立った思いを持ちつつ不平を言っていたのです。「そこで」イエスは「3つの(アポリューミの)たとえ」を語られました。これは勿論、罪人たちとファリサイ派の人々に聞かせるためです。この「たとえ」には罪人の悔い改め(立ち帰り)の為に注がれる神の愛が強く描かれていますが、それと共に私共に悔い改めの真実とは何かを悟ることが求められているのです。3つのたとえに登場する主人公は「羊飼い」「女」「威厳のない父」です。この物語や主人公の内容を聞く時、ファリサイ派の人々は「罪人の話」として聞き、心地良く話を聞くことができません。しかし、この話は「イエス」「聖霊」「神」が今、失われている魂(罪人)の為に、心を砕き、体裁を考えずに、魂の救いの為に働き、罪人が神の元に立ち帰る(悔い改め)ならば、誰よりも一番に喜んで下さるという意味のたとえとなっています。ファリサイ派の人々に、その意味は届いていません。ですから最も大切なたとえである「放蕩息子」に兄を登場させ、兄が彼らであることを示したのです。兄は自分を正しい者としていますが、兄もまた罪人です。父を軽蔑しているからです。また、このことは「家に入ろうとせず」に象徴的に示されています。兄もまた弟のように家(父である神)から離れ、祝宴(天国)の招きを拒否しているのです。兄が、この後、どのような行動をしたかは語られていません。私(あなた)の心に委ねられているのです。主イエスは罪人が悔い改め、神の元に立ち帰り、本来の姿(神の似姿)に生きることを願っておられます。