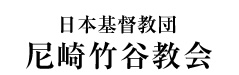「聖 書」
「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」そしてまた、身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と、立ち去ってしまい、イエスひとりと、真ん中にいた女が残った。イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。」女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない。」
(ヨハネによる福音書 8章1~11節)
「これからは、もう」
いよいよ次週に「受難週」を迎えます。先週の礼拝においては「放蕩息子」が読まれ、「悔い改めの真実」について御言葉に聴きました。本日の物語は、「悔い改めの命」について御言葉に聴きます。本日の出来事は祭司長たちが主イエスを捕縛に失敗した後の話です。もしかすると、ファリサイ派の人々が「放蕩息子」の話を聞いた後かもしれません。イエスが私達を非難していると受け取っていたでしょう。宗教権力者たちは何とか主イエスの失点を画策しました。それが本日の物語です。本日の物語は小括弧で挿入されています。新しい写本だからです。本来は、この処に記されてあった物語です。何故、編纂時に外されたのか。それは主イエスが「罪ある女」に「わたしもあなたを罪に定めない」と宣言しているからです。主イエスの真意は何か。ここを読む者の中に、どのような罪を犯しても、この聖書の言葉を引き合いに出し、「私の罪は許されている」と曲解する者がいたという記録は古にもありました。この美しい物語は、そのような矮小されたものではありません。これは「十字架の美しい物語」です。本日の御言葉は私共に自らの罪を示し、悔い改めの機会を与えます。しかしその機会は、私共の自由意志に委ねられています。御言葉の真意に迫りましょう。主は祈りの山から下られ、朝早く、神殿の境内に入られました。そこに民衆が皆(ラオス)、主のところにやって来ました。主は座って、「説教」をされました。神の民(ラオス)が、そこにいたのです。そこに律法学者たちが姦淫の現場にて捕らえられた女を衆目の前に連れて来ました。主に姦淫の女の罪を裁いてくれと「試み」に来たのです。イエスは彼らには答えずに、地面に何かを書き続けられました。この理由は何でしょう。沈黙することで自らの残虐性を顧みさせた等いろいろ考えられます。雨宮神父は御言葉(神はいのちを与える方)を書いておられたのではと解されています。私は主は裁き主なので、ここにいる一人一人の罪を書いていたのではないかと想像したりします。その何れにせよ、主が「罪を犯したことがない者が石を投げよ」と答えた時、全てが立ち去りました。私達は正義を振りかざさない「しない自由」を持っています。また「許す自由」も持っています。主は「わたしも罪に定めない」と言われました。赦しが命を与えるのです。女は、その後、十字架に出会い、赦しの源を知り、主の証人になりました。