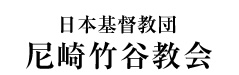「聖 書」
キリストは神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、すべての舌が、「イエス・キリストは主である」と公に宣べて、父である神をたたえるのです。
(フィリピの信徒への手紙 2章6~11節)
説 教「このため、神はキリストを高く上げ」
本日の御言葉は「キリスト賛歌」と呼ばれるものです。この賛歌は初代教会で讃美歌として歌われたとも言われています。本日9月14日は、カトリック教会では「十字架称賛」の祝祭が祝われます。西暦320年にローマ皇帝コンスタンティヌスの母ヘレナがエルサレムで十字架の遺物を発見した伝承に基づいています。聖遺物は十字軍とも結びついていきますが、この発見についてはヘレナの純粋な信仰を思います。しかしヘレナを言うに及ばず、多くのキリスト者は「十字架」に救われ、今も主の十字架に感謝を捧げ、思いを寄せる者です。この出来事は神秘です。神の業です。キリスト教の骨格を為す出来事は全て、人の知恵では理解できることではありません。神の業は「信仰により」、信じて、受け入れる出来事なのです。本日の御言葉には「受肉」と「謙卑」の姿が描かれています。2章6節に「キリストは神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず」とあります。(新改訳)では「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず」となっています。「身分」は、(モルフェー)で「かたち・本質」を意味する語です。後節の「人間の姿」は「外形」を表す(スケーマ)です。子である神イエスは「受肉」により人間となられました。その意味は7節の「自分を無にして(ケノオー)」に繋がる神の愛です。神は何でも出来るお方です。「無にすること」は神性を捨てたのでなく、ただ神的権威を捨てたのです。これが真の「遜り」(タペイノス)の意味です。では私達は「真の遜り」を生きることができるのでしょうか。キリストに倣う弟子の人生を歩んでいくことができるのでしょうか。ここに以前に、お交わりのあった武田師の作られた歌があります。お聴きください。(聴く)武田先生は、「迷いの時期の心の叫びを歌にしました」と言われました。信仰者の、御言葉を取り次ぐ者の真摯さを思います。「主よ、私を 聖めて、その手で形を造り、祈りの器にして、永遠の愛を注いで」の箇所などは涙が込み上げてくるところです。私共キリスト者は「ケリュグマ」(福音:神の業)を信じて受け入れた者です。そして「ディダケー」(主の教え)を教え、語って来た者です。その中で、自分の信仰は問われてきました。「本当に信じているのか」と。私共は、神の愛を生きる「ディアコニア」(仕える)にも生きてまいりました。その経験の中で、「まことの愛か」と問われてきました。私共の前を歩まれた先達も又同じです。私共は問われて良い。私を問いつつ、前に進めて下さる方が主であるからです。