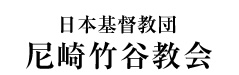「聖 書」
ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と言われた。
イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのを御覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また、少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に舟に残して、イエスの後について行った。
(マルコによる福音書 1章14~20節)
説 教 「福音を宣べ伝える」
イエス様は公生涯の初めに、「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。」と語り、神の福音を宣べ伝えられました。本日は、この主の「第一声」から御言葉の恵みに触れたいと願います。さて、本日イエス御自身が語られる「福音」という言葉ですが、皆様もよく知っている言葉です。ではキリスト者ではない人に、この「福音」という言葉を説明するとするならば、皆様は、どのようにお語りになるでしょうか。例えば、「良き音信(おとずれ)」や「グッドニュース」でありましょうか。あるいは「魂の救い」を熱心に語るということをなさるかもしれません。その意味は勿論正しい捉え方の一つではあります。しかし、その説明はパウロの手紙に記された「福音」の捉え方です。新約聖書の中には「福音」という言葉が76回出てまいりますが、その多くがパウロ書簡に記されています。福音書の中では12回用いられています。この「福音」という言葉は、一律ではなく、前後の文脈を解して読み解くものです。ではイエス様は本日の言葉を、どのような意味で語られているのでしょうか。そのことを解き明かす前に、旧約聖書では「福音」(ベソラー)はどのように用いられていたかを見ておきましょう。イエス様が「福音」を語られる前の、「福音」とは世的な意味をもっていました。それは「戦勝の知らせ」であり、「戦勝による褒美」を意味していました。(サムエル記4章)そのことを知るとき、イエス様が用いられた「福音」という言葉は全く別のものであることは理解されることでしょう。本日の御言葉を読み解くための「鍵」があります。それは「神の福音」であり、「時は満ち」です。本日の御言葉は共観福音書のすべてに記されています。しかしマタイ書ルカ書はマルコ書を底本にしているにもかかわらず、先ほどの二つの鍵の言葉を用いていません。マルコ書は主の語る「福音」(エゥアゲリオン)に特別な意味を込めていることを解さなければなりません。「神の福音」の「の」(トォウ)は属格です。つまり「福音」は神の「賜物」という意味です。また「時は満ち」の「時」(カイロス)は神の「決定的な時」を意味しています。では神は、決定的な時に何を私達に賜物として与えられたのでしょうか。それは「イエス御自身」です。旧約の「福音」は一時的なものであり、世的なものです。新約の「福音」は永遠に続くものであり、霊的なものです。イエス御自身は言葉の受肉です。私共もまた神の福音により、御言葉に生き、主と同じ命を生きる者へと変えられていくのです。