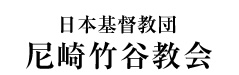「聖 書」
朝早くまだ暗いうちに、イエスは起きて、人里離れた所へ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけると、「みんなが捜しています」と言った。イエスは言われた。「近くのほかの町や村へ行こう。そこでも、わたしは宣教する。そのためにわたしは出て来たのである。」そして、ガリラヤ中の会堂に行き、宣教し、悪霊を追い出された。
(マルコによる福音書 1章29~39節)
説 教 「わたしは宣教する」
本日の御言葉は21節から39節が一括りの物語となっています。そこにはカファルナウムで一日を過ごされた主の姿が描かれています。一般的にイエス様の生涯の働きを凝縮した一日と言われています。その意味は、まず場所が会堂から始まり、家、家の戸口と移り変わっているところから、会堂(宗教生活)家(個人生活)家の戸口(公の生活)の意味とされ、イエス様の業が人間生活全般に及んでいたということを示しています。また記された一日の中でイエス様は「教え」「悪霊を追い出し」「癒し」そして「祈り」をされています。これらのことは主の業そのものを示しています。つまり本日の御言葉は、イエス様の公生涯の意味を知るのに最適なものであると言って良いでしょう。また、そう受け取ることがマルコ書の意図でもあります。では、イエス様の公生涯の中で最も大切な業は何であったのでしょうか。それは「教え」(ディダケー)です。本日の御言葉でもイエス様は「奇跡の癒し」もされていますが、その「癒し」よりも「教え」が最も大切な主の業なのです。このことは特にマルコ書に特徴的に述べられていることです。マルコ書では「教える」(ディダースコー)は16回用いられていますが、その用いられ方のほとんどが、イエス様が主語で、未完了形で書かれています。それもイエス様が「宣教を述べる」時にだけ用いています。マルコ書はこの特徴的な用い方を通して、イエス様の宣教には特別な力があることを示そうとしています。本日の御言葉でも、イエス様が多くの奇跡の癒しを為された後、多くの人々がイエス様に癒していただこうとイエス様を捜している場面が描かれています。そのことをシモンの口を通して、「みんなが捜しています」と言わせています。イエス様の奇跡に出会い、多くの人々が押し寄せて来る気持ちはよく分かります。イエス様も、そのことはよく理解していたにも関わらず、あえて朝早くから「人里離れた所」へ行き、群衆との距離を置かれました。これは、イエス様の奇跡の意味を悟らせる為です。主はシモンの問いかけに、「近くの町へ行こう。そこでも、わたしは(このことを)宣べる。」と返しました。イエス様の公生涯の意味を知らせる為です。イエス様の奇跡は宣教内容の正しさを裏付ける「しるし」です。イエス様の世に来られた目的は、「人間生活のあらゆる場から悪霊を追い出し、神の国を実現する」為です。イエス様の「癒し」には神の力が働いています。そのことを悟ることができた時、人は神を身近に知り、救いを知るでしょう。それが宣教です。