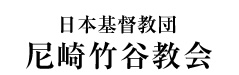「聖 書」
キリストは、肉において生きておられたとき、激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いをささげ、その畏れ敬う態度のゆえに聞き入れられました、キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして、完全な者となられたので、御自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源になり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。
(ヘブライ人への手紙 5章7~9節)
説 教 「永遠の救いの源」
主の受難が近づいてまいりました。本日は「主の受難」の意味について御言葉に聴きましょう。さて、本日の御言葉の鍵言葉は何でしょう。それは大祭司でなく、「従順」です。ヘブライ人への手紙はお気づきのように、「○○の信徒への手紙」のように「信徒」という言葉が入っておりません。この意味は異邦人キリスト者に向けて、「大祭司キリスト論」を神学的論文として書いたものと解されるからです。ヘブライ人と記されていますが、この意味は、ヘブライ語を話すユダヤ人ヘブライニストとギリシャ語を話すヘレニストの両方に向け、書かれています。この手紙はユダヤ教を説明しつつ、ユダヤ教の限界を語っています。つまり、本日の手紙は、ユダヤ教の限界性を語りつつ、律法の完成者であるキリストを語ることにより、既に「永遠の救い」が用意されていることを語っているのです。私共は今、レントを過ごしていますが、この時期は自分の罪の大きさに嘆くことも多くあると思います。しかし、既に「永遠の救い」が用意されていることは大いなる恵みです。では、その「永遠の救い」はどのように用意されたのでしょうか。それは本日の説教題に記した如く、「永遠の救いの源」が用意されたからです。では、その「源」とは何でありましょうか。それが主の「従順」なのです。主の「従順」は「主の受難」と同義です。主は本日の御言葉が語る如く、「激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いをささげ」られました。何を祈られたのでしょうか。それは私共の「罪の贖い」です。本日の鍵言葉である「従順」はフーパーコエーであり、「絶対服従」を表しています。「絶対服従」は強制を表しているのではなく、強い絆や強い「信頼関係」を表しています。神と主との「信頼関係」のことです。イエスの「受難」とは一体何なのでしょうか。それは人への「愛」です。イエス様は神との強い信頼関係の中で、神の子メシアの責務を果たそうとしています。それは人々の罪を背負い、その死をもって贖うために十字架に赴くことです。これが「主の受難」です。私達には、どのような罪があるのでしょうか。それは「垣根」「不和」「争い」「自己中心」です。初代教会のユダヤ人と異邦人、ヘブライニストとヘレニスト、異なる宗教等、当時も多くの「垣根」(罪)が存在しました。それを永遠の大祭司メルキゼデクであるキリストが、その全ての垣根を取り除くために十字架の死を遂げられました。愛を貫き通されました。私共は、この愛の完成に信頼して歩むのです。