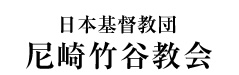「聖 書」
「恐れることはない。ただ信じなさい」と会堂長に言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは、だれもついて来ることをお許しにならなかった。一行は会堂長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り、人々に言われた。「なぜ、泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ。」人々はイエスをあざ笑った。しかし、イエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいる所へ入って行かれた。そして、子供の手を取って、「タリタ、クム」と言われた。これは、「少女よ、わたしはあなたに言う。起きなさい」という意味である。少女はすぐに起き上がって、歩き出した。もう十二歳になっていたからである。それを見るや、人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことをだれにも知らせないようにと厳しく命じ、また、食べ物を少女に与えるようにと言われた。
(マルコによる福音書 5章21~43節)
説 教 「手を取って」
先日の「聖会」において、私は「福音」についてお語りしました。そして福音を生きるとは如何なることかということもお語りいたしました。「ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。」(フィリピ1:27)この言葉は命を生きることであって、教条的な意味として受け止めてはならないともお語りしました。その本質的な意味を本日の御言葉は見事に語り抜いています。本日の御言葉は、二つの治癒奇跡の物語が記されています。その構造はヤイロの娘の「治癒(甦り)物語」を中断させる形で、イエスの服に触れる女の「治癒物語」が挟み込まれています。これは著者の意図です。マルコは物語を中断させて、別の物語を挟み込む手法をよく用います。(6:14-29等)何故そのようなことをするのかと言いますと、本編の物語の中心を明確にするためです。本編を補完しているのです。本日の御言葉では、ヤイロの娘の物語をイエスの服に触れる女の物語が補完している形になっています。ではどのような補完なのでしょうか。このことは本編のヤイロの娘の「治癒(甦り)」をどのように受け止めるのかという信仰の問題とも関わっています。それでは補完の物語の「イエスの服に触れる女」の方から見ていきます。この女は長血の患いによって「汚れ」規定の中にありました。(レビ15:25)規定により人に「触れる」ことができずにいたのです。その女はイエスの噂を聞きつけて、「その方の服にでも触れればいやしていただける」と思い、それを実行に移しました。古代にあっては、服は、その人の一部という考えがありました。女はすぐに癒されました。女はそのことをすぐに理解しました。物語としては、ここで締めではないでしょうか。何故イエス様は、女を探したのでしょうか。それは「癒し(健康の回復)」が、即その女の「救い」ではないことをイエス様は理解していたからです。女はイエス様から見出され、対話をしました。そして、「元気に暮らしなさい。」と言われたのです。この「元気」は「平和(エイレーネー)」です。この女の「救い」とは癒しの魔術ではなく、イエス様との対話的「触れ合い」こそが、「永遠なる救い」であるとマルコは語っているのです。ではヤイロの娘の治癒(甦り)は如何様に受け取れば良いのでしょうか。聖書の「奇跡物語」は「何を伝えているかを知ること」がとても大切になってきます。娘の甦りは、主の「手を取って」から始まります。これは「触れる」と同じ意味です。復活は単なる甦りではなく、死を滅ぼす神との出会いであるとマルコは語っているのです。