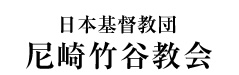「聖 書」
イエスは、弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、「人々は、わたしのことを何者だと言っているか」と言われた。弟子たちは言った。「『洗礼者ヨハネだ』と言っています。ほかに、『エリヤだ』と言う人も、『預言者の一人だ』と言う人もいます。」そこでイエスがお尋ねになった。「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが答えた。「あなたは、メシアです。」するとイエスは、御自分のことをだれにも話さないようにと弟子たちを戒められた。
それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている、と弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話しになった。
(マルコによる福音書 8章27~35節)
説 教 「福音のために」
マルコ書は、本日の御言葉を境に、前半と後半に分かれています。つまり本日の御言葉はマルコ書の中心となります。本書の中心は「キリスト告白」です。マルコ書の冒頭もまた「キリスト告白」となっています。著者は本書を読む人に強く「キリスト告白」を迫っています。また、イエスに出会う全ての者に、「あなたはイエスを誰というのか」という問いも投げられているのです。本日ペトロは見事に「キリスト告白」を為しましたが、イエス様が「キリストとは受難を受ける者である」という答えを返した時に、彼は主を「いさめ」ました。並行記事のマタイ書には「そんなことがあってはなりません。」(マタイ16:22)と記されています。この原意は「神の慈しみが、あなたを守るからそんなことはありえない。」ということです。この言葉は「上から目線」(自分が正しく優位にある)のものであっても、善意の発言でありましょう。イエス様はペトロを「叱責」しました。「サタン、引き下がれ」と言われたのです。これは如何なる意味なのでしょうか。この意味はマタイ書4章の「誘惑を受ける」場面を思い起こして頂ければ、お分かりになるでしょう。イエス様は公生涯に入る前に「荒野の40日」を過ごされました。メシアの使命を受けるためです。荒野では神と共に、悪魔の誘惑もありました。悪魔はメシアとして遣わされる主に、そんな「受難」を受けずとも、神の子の力を見せつければ、皆が納得するではないかと言うのです。その時の言葉が、聖書の言葉を用いて、「(飛び降りても)神の慈しみが、あなたを守るだろう。」(マタイ4:6)でありました。イエス様は、その時のことを思い起こされ、ペトロを「叱責」されたのです。「叱責」と「いさめる」はともに(エピティマオー)が用いられていて、二人のメシア理解の相違と対立を際立たせています。(ここに至る解き明かしの構造は以前のものを参照下さい。2012.9.16参照)私共も主イエスを「キリスト」と告白致しました。そのキリスト理解は、「自己本位」のものにはなってはいないでしょうか。私は、自己本位になってはいないということを知る方法はあります。それは「主の言葉に従う」ことです。具体的には、本日の御言葉が語るように生きることです。それは「自分を捨てること(イエスの権威と言葉に聴くこと)」「自分の十字架を背負うこと(自分の十字架を選び取ること)」「主に従うこと(主の権威と言葉に聴き従うこと)」この生き方を為すときに、「福音のために」遣わされ、死を越える命を生き、永遠の幸いを生きる者とされるのです。