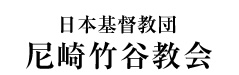「聖 書」
ユダヤ人の過越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ上って行かれた。そして、神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと、座って両替をしている者たちを御覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。「このような物はここから運び出せ。わたしの父の家を商売の家としてはならない。」弟子たちは、「あなたの家を思う熱意がわたしを食い尽くす」と書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、「あなたは、こんなことをするからには、どんなしるしを見せるつもりか」と言った。イエスは答えて言われた。「この神殿を壊してみよ。三日で建て直してみせる。」それで、ユダヤ人たちは、「この神殿を建てるのに四十六年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのか」と言った。イエスの言われる神殿とは、御自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちは、イエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。
(ヨハネによる福音書 2章13~25節)
説 教 「家を思う熱意」
本日の御言葉は、主イエスの「宮きよめ」の場面です。本日の記事は全ての福音書に記されていますが、ヨハネ書と共観福音書においては、少しの差異が見られます。本日は、そのところも照らし合わせながら、御言葉の解き明かしを致します。共観福音書においては、「宮きよめ」はエルサレム入城後の受難直前の出来事として記しています。ヨハネ書においては著者は福音書の冒頭に「宮きよめ」を記しました。その意味は前節で記された「カナでの婚礼」と「宮きよめ」を対として置き、主イエスの「受難」と「復活」の意味を象徴的に語るためです。ヨハネは主イエスの到来が霊の「新しい時代の幕開け」であることを冒頭で宣言したのです。ヨハネは主イエスは「受難と復活」を通して「新しい神殿」となられるということを、その始めに語りました。「宮きよめ」の行為の後に、ユダヤ人たちは、主に、「どんなしるしを見せるのか」と詰めました。彼らは世のしるしを求めています。主イエスの「しるし」は「神の栄光」です。彼らの求めるものとは違います。本日の場面は世の人と霊の違いが、はっきりと示されている場面でもあります。(2:25)「イエスは、何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。」皆様は、本日の「宮きよめ」の場面を主イエスの乱暴な出来事として感じられるでしょうか。本日の出来事は宮の庭でのことです。その場所は「境内」です。神殿の外の部分で「異邦人の庭」と呼ばれていました。神殿の内側は区別されていて、ユダヤ人しか入ることはできませんでした。ユダヤ人は神殿に異邦人がいることやローマに支配されていることを苦々しく思っていましたが、世的な対応をしながら礼拝を守ったのです。これは現代にもある問題です。イエスが宮きよめをしている時に、弟子たちが加勢しなかったことにも、その世的なところを汲み取ることができます。ではイエスの行為の真意は何でしょうか。そのことは「家を思う熱意」(詩篇69:10)です。弟子が思ったことは、主の純粋性であり、神への愛です。この御言葉は苦難の中にあっても、神への信頼を持ち続け、まことの希望を手にする詩です。この引用は本書のみで、共観福音書では語られずに、「祈りの家」(イザヤ56:7)が、別に引用されています。これは「異邦人の救い」を語る御言葉です。四福音書は同じことを告げています。主の「家を思う熱意」が祈りの家を実現させたことを。