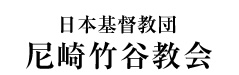「聖 書」
一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアにさしかかったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして、言われた。「向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだだれも乗ったことのない子ろばのつないであるのが見つかる。それをほどいて、連れて来なさい。もし、だれかが、『なぜ、そんなことをするのか』と言ったら、『主がお入り用なのです。すぐここにお返しになります』と言いなさい。」二人は、出かけて行くと、表通りの戸口に子ろばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。すると、そこに居合わせたある人々が、「その子ろばをほどいてどうするのか」と言った。二人が、イエスの言われたとおり話すと、許してくれた。二人が子ろばを連れてイエスのところに戻って来て、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また、ほかの人々は野原から葉の付いた枝を切って来て道に敷いた。そして、前を行く者も後に従う者も叫んだ。
「ホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように。我らの父ダビデの来るべき国に、祝福があるように。いと高きところにホサナ。」
説 教 「来るべき国」
本日は「棕梠の主日」です。「受難の主日」とも言われます。つまり、本日から受難週に入り、聖金曜日の「受難日」を迎える週に入ったということです。私共は、どのような心で受難週を過ごせばよいのでしょうか。勿論、救いに与っている私共は恩寵の喜びの内に過ごせば良いのです。その意味を深く知るために、本日の御言葉が用意されています。本年はマルコ書を中心に御言葉に聴きますが、先週までヨハネ書も用いましたので、本日は「受難」を両書から聴くことと致します。カトリックでは、本日のミサを「枝の主日」と申します。司祭は「枝」を祝別します。信徒は、その枝を振りかざして、「勝利の王キリスト」を迎えます。本日の「エルサレム入城」の場面と同じです。しかし、その意味は根本的に違います。カトリックの「迎え」は、「永遠の王キリスト」と共に永遠の都エルサレムに入ることを意味しています。本日の場面のエルサレム入城の後には何がありますか。イエスの「受難」です。この違いは、どこから来るのでしょうか。それは、「来るべき国」(11:7)を見ている先が違うのです。イエスを迎えた人々は「メシア」を迎えたのです。しかし彼らの望んでいたメシアは、ローマの圧政から救う「王」です。イスラエルを再建してくれる王です。その彼らの思いに適わない者であったので、主は侮辱を受けたのです。主イエスの完成された「来るべき国」は「永遠の御国」です。彼らは思い違いをしていたのです。彼らは「ホサナ」と主を迎えました。この意味は「どうか、救って下さい」(詩篇118:25)ですが、彼らは、本来の意味ではなく歓呼の「万歳」として用いたでしょう。本来の意味は「懇願」で、仮庵の祭りで用いる枝の束(ルーラブ)に「水」を含ませ、祭壇に水を注ぎ、渇いて萎れていく柳の枝を横に、「ホサナ」(主よ、救って下さい)と叫ぶのです。ヨハネ書は文字通りの意味で、主を「永遠の泉」(ヨハネ7:37)として告白しています。マルコ書は受難を中心に描いています。にも拘わらず、主は「メシアの秘密」(ウレーデ)として描かれ、(ヨハネ書とは対称的です。)受難の場面も「沈黙」(別紙参照)を貫かれています。この意味は深遠です。私共は沈黙の十字架に向き合うのです。主は大声で「成し遂げた」と叫び、息を引き取られました。世の偽の王の誘惑を退け、侮辱を忍び、神の計画(福音)を成し遂げられました。私共は沈黙の中にある愛を信じる者です。