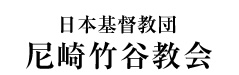「聖 書」
徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と不平を言い出した。そこで、イエスは次のたとえを話された。…イエスは言われた。「ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言った。それで、父親は財産を二人に分けてやった。何日もたたないうちに、下の息子は全部を金に換えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。…ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。』しかし、父親は僕たちに言った。『急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』そして、祝宴を始めた。
(ルカによる福音書 15章1~3,11~32節)
説 教 「父親は息子を見つけて」
四旬節第四主日を迎えました。「霊の祝福を生きる」ことは「神に立ち帰る」を意味しています。本日の御言葉は、そのことを表しています。四旬節の大切な時、「まことの立ち帰り」を経験いたしましょう。キリスト者の「戦い」「目標」「勝利」を御言葉から聴いてまいりました。本日は「幸い」です。キリスト者の幸いは「主の前に額ずくこと」(礼拝)です。先週の「モーセの召命」は正に、その場面でした。(聖壇前のメノラーと十字架)私は、この召命の場面の主人公は神であると申し上げました。私共が立ち帰る場所には、まず「神の愛」があるのです。この「放蕩息子」の話も又、神が主人公です。理解しやすい「たとえ話」ですから、自分は弟だとか、兄の気持ちも分かるとか思いながら「たとえ話」を読むことでしょう。しかし、この「たとえ話」は「神の愛」と「神の痛み」を知ることが中心です。主は15章で「話を聞こうと近寄って来た罪人の皆」と「罪人と食事を共にすることに不平を言う律法学者たち」に「3つのたとえ」を語られました。「3つのたとえ」をよく読むと、「大切なものを失った主人公」が、それを「見出し」回復を喜ぶ姿が描かれています。それは罪人の悔い改め(立ち帰り)のことであり、それは神の喜びであり「天の喜び」(祝宴)であると主は解き明かししておられます。私は我が子を失いそうになった経験をしたことで、神が「恥も外聞も忘れて愛する子のところに行く父の気持ち」を理解することができます。「放蕩息子」に出てくる「父」は律法学者たちには「ダメ親」です。放蕩息子には罰を与え、償いをさせる必要があると彼らは考えます。その考えに反し、父親は「走り寄り」(権威を捨てる)、自ら恥をかき、良い服を与え、指輪をはめ、履物を履かせるのです。そして祝宴をするのです。長子が得る特権です。この行為の全てが「ダメ親」の行為を意味しているのです。後に続く兄の怒りや父への無理解もここに起因しています。この兄の姿は律法学者たちです。救いは恵みではなく、「行い」であると断じているのです。私共の前に「十字架」があります。十字架は「恥の象徴」です。何故、神は十字架を御子に負わせられたのか。それは、私共の決して「負いきれない不安」「負いきれない痛み、悩み」を担い切るためです。私共が「担い切れない重荷」を主の前に置くとき、神の権威を捨て、恥も外聞も忘れた「十字架の愛」がそこにあります。「父の極みの愛」です。私共の「幸い」は、私共の立ち帰りを神様に発見してもらうことです。そして完全な神の愛(十字架)の前で憩うことです。