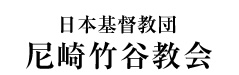「聖 書」
使徒たちの手によって、多くのしるしと不思議な業とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、ほかの者はだれ一人、あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし、民衆は彼らを称賛していた。そして、多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人のだれかにかかるようにした。また、エルサレム付近の町からも、群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まって来たが、一人残らずいやしてもらった。
(使徒言行録 5章12~16節)
説 教 「その数はますます増えていった」
本日の御言葉は「使徒の働き」です。先日召された教皇様も使徒の働きを大切にされました。週報を御覧下さい。「教皇講話集」の一つに「使徒言行録・世をいやす」があります。「いやす」は(セラペイア)です。本日の御言葉の最後の句にも用いられています。ペトロ先生は「いやし」を得ました。彼が癒された秘訣は、「信じる心」(ピスティス)です。復活の主は聖トマスに「信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」と言われました。(ヨハネ20:28)召天された教皇様は「使徒言行録」の講話の中でペトロとパウロを取り上げ、聖霊の働きについて語られました。「聖霊が、おられなければ福音宣教はありません。福音宣教とは聖霊に導かれるようにすることです。」本日の御言葉の中にある「多くのしるしと不思議な業」は使徒たちの手によってなされたと記されていますが、原文を見る限り、前置詞の活用法は「(他の働きによって)行われた」と採る訳が正しいのです。つまり使徒の働きは「聖霊の働き」であったということです。先日、牧師会がありました。交わりの中で、ある牧師が言われました。「信仰のことは信徒に聞いて下さい。」どのような意味か分かりますか。続けて、牧師は「わたしは御言葉に専念します。」と言われたのです。私は深く感銘し、共感を致しました。信徒が、お聞きになりたい実際上の「信仰の質問」は、最も役に立つ回答(近しいの意味)を持っているのは先輩のキリスト者です。まことに健全な答えだと思います。原始教会の時代から信徒は増え続けました。雑務が増え、執事が生まれました。使徒たちは「祈りと御言葉に専念する」ことにしました。「交わりの信仰」を健全に保つ為に「祈り」と「御言葉」が大切であったからです。しかし皆様は、本日の御言葉を聞いて、不思議に思われないでしょうか。主イエスが十字架の死を遂げられて、まだ日が浅い時なのです。あの十字架の出来事を覚えている人たちがここにはいるのです。その中で使徒たちは大胆に福音を告げ、宣教しているのです。その後、「多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった」のです。教皇様は講話の中で、このようなことを語り、信徒に勧めをされました。「自分で使命を「でっちあげる」ことではなく、霊で心をダイナミックに動かして下さる御父を待つことをしなさい。」使徒たちの業は「御旨」なのです。この御旨は何か。「一人残らずいやしてもらった」(5:16)神の御旨は全ての人を残らず救うことです。主の御旨が「本物の教会」を造り、愛の交わり、救いの場所となり、帰る場所、人々の癒しの場所となるのです。