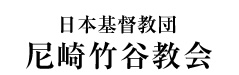「聖 書」
貧しい人は食べて満ち足り、主を尋ね求める人は主を賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように。
地の果てまで、すべての人が主を認め、御もとに立ち帰り、国々の民が御前にひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命に溢れてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に降った者もすべて御前に身を屈めます。
わたしの魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来るべき代に語り伝え、成し遂げて下さった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。
(詩篇 22編1~31節)
さて、昼の十二時に、全地は暗くなり、それが三時まで続いた。三時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」これは、「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」という意味である。
(マタイによる福音書 27章11~54節)
説 教 「成し遂げて下さった恵み」
本日は「棕櫚の主日」です。本日から「聖週間」(受難週)が始まります。この一週間の「早天祈祷会」は致しませんので、どうぞ本日聴く御言葉を深く受け留め、ご自宅にて「黙想の時」をお持ち下さるように願います。本日の御言葉は二つ用意致しました。主の弟子達が「主の受難」を如何に解したかを知るためです。次週の「復活主日」では使徒言行録を用いて、ペトロが「復活」を如何に解したかを聴きます。「受難」も「復活」も歴史的な事実ですが、この事実は信仰の目を通して悟ることこそが最も大切なことです。弟子達の「証言」を聴くことを通して、神の大いなる業に感謝を捧げる魂が整えられるように主に希います。さて本日の御言葉は福音書では「主の受難」の場面です。先に旧約の詩編22編をお読み致しました。皆様もよく御存知のように、「主の受難」の場面では旧約の言葉が13箇所用いられています。その内の8箇所は詩編22編からのものです。この意味は如何に捉えればよいのでしょうか。これは予言の成就を語っているのでしょうか。それはそうではありません。主の受難に出会い、聖霊の油注ぎを受けた弟子達が、「詩編22編」を「主の受難」として解釈したのです。ですから同じキリスト者である私共も又、弟子達の「信仰体験」に倣い、その解釈を「私の信仰」として捉える必要があります。主は十字架上で、息を引き取られる時に「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われました。詩編22編の言葉です。「エリ」は「我が神」の意です。主は神を「父よ」と呼ばれました。「我が神」という言い方はされませんでした。つまり主の発せられた「詩編22編」は私共(罪人)の身代わりの言葉であったという意(解釈)です。その最期の言葉をヨハネ書は「成し遂げられた」と言われたと告げています。詩編22編31節の言葉です。「成し遂げて下さった恵み」と記しています。詩編の記者は「何を」「成し遂げて下さった恵みの業」と言っているのでしょうか。それは(罪ゆえに)神に見捨てられる自分が、神の愛(贖い)の業によって、「魂が命を得る」という意味です。詩編22編は「遺棄される者の叫び」の詩ですが、その叫びは神に届き、「貧しい人」は満ち足り、「主を賛美」しますと「賛歌」となっています。つまり弟子達は十字架の死は、私共の罪の贖いの死であって、その神の極みの愛は「貧しい人」を「魂の救い」に与せる神の恩寵であったと弟子は証言したのです。