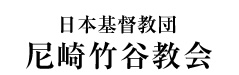「聖 書」
すると、長老の一人がわたしに問いかけた。「この白い衣を着た者たちは、だれか。また、どこから来たのか。」そこで、わたしが、「わたしの主よ、それはあなたの方がご存じです」と答えると、長老はまた、わたしに言った。「彼らは大きな苦難を通って来た者で、その衣を小羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ、彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。彼らは、もはや飢えることも渇くこともなく、太陽も、どのような暑さ、彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる小羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へと導き、神が彼らの目から涙をことごとくぬぐわれるからである。
(ヨハネの黙示録 7章9~17節)
説 教 「命の水の泉へ」
先週の御言葉はヨハネ書21章でした。説教においても語った如くに、復活の主に出会うとは、「新しい出発」を為す事です。その出発は「愛の回復」を基にしながら、「霊的な命の中を生きる」ことであり、主に遣わされる「派遣の命」を生きることです。では、その命の中や派遣を歩む者は何を手にするのでしょうか。それは、本日の御言葉が記す「命の水の泉」を手にすることができます。では「命の泉」とは何でしょうか。西洋においては、聖書に端を発した
「命の木」にまつわるエピソードとして、「不老不死の水」の伝説として、人の欲望に根付いた荒唐無稽な話として知られています。しかし聖書が記す「命の水の泉」とは「不老不死の水」のことではありません。「命の水の泉」とは、汲めども尽きない「霊的命」のことです。ヨハネはヨハネ書4章10節において、「その人は生きた水を与えたことだろう。」と語っていますが、この「水」のことです。また同じ章の13、14節に、「イエスは答えて言われた。「この水を飲む者はだれでもまた渇く。しかし、わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。」この主が語られた「泉」こそが、「命の水の泉」のことです。これは何を語っているかというと、「霊的な飢え渇きを癒す水」のことを語っています。詩編42編を御覧下さい。「涸れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、わたしの魂はあなたを求める。神に、命の神に、わたしの魂は渇く。」この「魂の渇き」を癒す水こそが、「命の水の泉」のことです。「泉」は「湧き出て」「流れて」「常に新しい」ものです。ですから、小羊である主から与えられる水も、汲めども尽きない「新しい豊かな霊的命」であるという意味が語られています。本日記された「白い衣」は「殉教者」を表しています。しかし本日の御言葉は、この後に続く「麻の衣」にも連なるテーマとして語られていますので、「命の水の泉」は殉教者だけではなく、すべての「キリスト者」に与えられるものとして捉えてよいでしょう。講壇の前のステンドグラスを見て下さい。三浦先生の作品です。「ヨハネの黙示録」の「7人の天使」が表されています。上部の円には「花が咲く鉢」が描かれています。聖書の記述にはありません。三浦先生の解釈です。聖書においての「鉢」のなかには「災い:裁き」があります。しかし先生は「花」を入れました。7人のラッパの後に生じる「新しい世界」を描くためです。私共も又、復活の主に出会い、新しい世界(命の泉)に生きます。