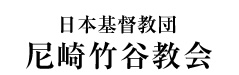「聖 書」
そこで、大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、ねたみに燃えて使徒たちを捕らえて牢に入れた。ところが、夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、「行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい」と言った。これを聞いた使徒たちは、夜明けごろ境内に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間が集まり、最高法院、すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集し、使徒たちを引き出すために、人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると、使徒たちは牢にいなかった。彼らは戻って来て報告した。「牢にはしっかり鍵がかかっていたうえに、戸の前には番兵が立っていました。ところが、開けてみると、中にはだれもいませんでした。」この報告を聞いた神殿守衛長と祭司長たちは、どうなることかと、使徒たちのことで思い惑った。そのとき、人が来て、「御覧ください。あなたがたが牢に入れた者たちが、境内にいて民衆に教えています」と告げた。そこで、守衛長は下役を率いて出て行き、使徒たちを引き立てて来た。しかし、民衆に石を投げつけられるのを恐れて、手荒なことはしなかった。
(使徒言行録 5章17~32節)
説 教 「この命の言葉を残らず民衆に告げなさい」
本日の御言葉は先週の続きです。「そこで」とあります。使徒たちが自分たちの忠告を聞かなかったことを受けてという意味です。主を十字架につけた宗教の指導者たちは「ねたみに燃えて」とあります。直訳すると「熱心が膨れ上がり」となります。自分の正義が燃え上がり、聴く耳を失い、周りが見えなくなっている状況です。これは誰しもが気を付けなければならないことです。5章から続く御言葉は一言で語るならば、「神を正しく畏れる信仰」です。使徒たちは、神を正しく畏れる信仰に生きています。このところの詳しいところは、先週の連合聖会の準備祈祷会でお語りしてきました。5章でよく語られるテーマは内の敵と外の敵です。私は少し違う捉え方をしています。「アナニアとサフィラ」ではペトロはアナニアに対して、「あなたは神を欺いたのだ」と語っています。本日の御言葉ではペトロは大祭司たちに「人間に従うよりも、神に従わなくてはなりません。」と語っています。ペトロたちには、「神の言葉に従う信仰」が、そこにあったことを語る言葉でもあります。使徒たちは「復活の証人」です。「福音の使者」です。本日の御言葉は「敵」の話ではないのです。「復活の証人」として生きることを語る御言葉です。牢から外に連れ出してくれた主の天使は、「この命の言葉を残らず民衆に告げなさい」と使徒たちに伝えました。「この」とは何か?あなたがた使徒たちが経験している「命」のことであり、「救い」のことを指す「この」です。私共も又、復活の主に出会い、「赦しを受け」、復活の命に起こされました。私共は「新しい命」に生き、新しい人の歩みを為しています。私共は礼拝者の人生を歩んでいます。それは「福音の使者」の人生を歩んでいるということです。私共の人生そのものが「福音」となるという意味です。本日の主の天使の奇跡は私共キリスト者が日常に経験していることです。主は私共の人生の「危うきを救う使者」を必ず送って下さっています。私共の人生は、「この命の言葉を全部告げる」ものへと神が導かれます。私共は福音を体現する道を行きましょう。その道は待ち望みが大切です。使徒たちは復活の主が昇天された後、聖霊と力(ドユナミス)を待ち望みました。(使徒1.2章)自分の言葉を発せず、主の言葉に従ったのです。そこに聖霊が降られたのです。ここで語られる「力」は主も持っておられたものです。「イエスの服に触れる女」の場面で、主の内から「力」が出ていったと同じものです。(マルコ5:30)信仰は神の言葉を選択し神の言葉に従っていくことです。福音の命に感謝を捧げます。