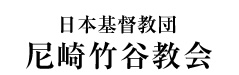「聖 書」
このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。
(ローマの信徒への手紙 5章1~5節)
説 教 「聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれている」
本日の御言葉は「ロマ書」です。パウロ先生の「遺言」とも言われます。1節に「わたしたちは信仰によって義とされた」とあります。勿論、「信仰義認」が語られているのですが、これは「ロマ書」の送り先の教会に「ユダヤ人と異邦人のユダヤ教の規定をめぐる対立」があったことに起因しています。「ロマ書」は「キリスト教教理の綱要」(メランヒトン)とさえ言われるキリスト教神学の基礎を語るものですが、本書は当時の情況を踏まえて出された「手紙」であることを忘れてはならないでしょう。つまり本書にはパウロ先生の「肉声」が聞こえてくるということです。本日の御言葉の中に、「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」という有名な言葉があります。これは「修練」を語るものでなく、「品性」(愛)を語るものです。フランシスコ会訳では、「練達」のことを、試練によって高められた信仰の状態(徳)「試練に磨かれた徳」と訳出します。「徳」とは「品性」であり、「愛」なのです。パウロ先生には「同労者」であるバルナバがいました。彼は名はヨセフであり、その品性を名にして、バルナバ(慰めの子)と使徒たちに呼ばれていたのです。彼は品性が「善」の人でした。敵対されていたパウロの味方をし、弁護し、教会の仲間に紹介しました。宣教に遣わされるときに、田舎に引きこもっていたパウロを探し出し、共に同労者の働きに加わるように促しました。宣教から逃げ出したマルコを反対されても宣教に同行させました。パウロはキリスト者の仲間の「真実な神の愛」が内住している姿を見て、常に励まされていたのです。パウロはキリスト者の内住のキリスト(聖霊)を見てとることができました。パウロ先生は本書をエフェソでの騒動後、第三回宣教旅行の後半のギリシャでの三か月を過ごす中で、認めました。ローマ教会(家の教会)の情況を踏まえて、スペイン伝道に赴く途中に立ち寄る、自分が立ち上げたのでない教会を励ますために本書を書きました。パウロがエルサレムに献金を届けた後に、ローマに向かうことは死を意味していることは理解していました。彼の滅びゆく魂へ「救いを届ける熱情」は神の愛そのものでした。彼の宣教の熱情は「神の愛」です。「宣教の愛」には苦難が伴います。苦難は忍耐を、忍耐は練達を生みました。「試練に磨かれた不動の愛」を彼は得ました。最後に先生は「希望」を得ました。先生の語る「希望」とは何か。それは最後の句です。「聖霊によって、神の愛が注がれている」この意は「キリストのようになる」ということです。聖霊の神の力が「聖化」の力です。