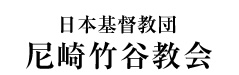「聖 書」
それで、わたしたちはいつも心強いのですが、体を住みかとしてかぎり、主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず、信仰によって歩んでいるからです。わたしたちは、心強い。そして、体を離れて、主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから、体を住みかとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれる者でありたい。なぜなら、わたしたちは皆、キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていたときに行ったことに応じて、報いを受けねばならないからです。
(コリントの信徒への手紙 二 5章6~10節)
説 教 「裁きの座」
本書の5章においては、「キリストによる神との和解」という福音のテーマがパウロによって語られています。それと共にパウロは「キリストの裁きの座」についても語っています。この二つ「和解」と「裁き」は矛盾しないのでしょうか。神は「聖」であって、人が心で思っただけの悪であっても「裁き」は神によって履行されます。神はそれほど完全なるお方です。またそれと共に神は「愛」そのものです。人を赦し、人を天国の住人にしたいと願っておられます。この二つのことを矛盾なく解決する方法は「ただ一つ」です。それはキリストの「十字架」です。では「十字架」とは何でしょうか。十字架の縦の木は、「罪なき方が全ての裁きを背負い、義と聖さを全うした完全な神の子の姿」を表しています。また十字架の横の木は「どこまでも私達を赦し、愛されている、私達の為に広げられた、愛と憐みに満ちた御子の姿」を表しています。裁きと和解の矛盾は「極みの神の愛」によって、既に解決済みなのです。パウロは後節にて語っています。「罪と何のかかわりもない方を、神はわたしたちのために罪となさいました。わたしたちはその方によって神の義を得ることができたのです。」(5:21)また「つまり、神はキリストによって世を御自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉をわたしたちにゆだねられたのです。」(5:19)と語っています。パウロは「和解の言葉」を委ねられたメッセンジャーなのです。では尚更、本日のパウロの語る「キリストの裁きの座」とは如何なる意味なのでしょうか。パウロがここで語る「裁き」とはキリスト者のみが受ける「裁き」のことです。聖書には三つの「裁き」の時と場所のことが語られていますが、詳しくは後日またお語りすることにして、本日は「キリストの裁きの座」のみお語りします。「キリストの裁きの座」のことを一言でお語りするなら、「私達キリスト者の人生への報酬を受ける場所」のことです。パウロは本日の言葉をコリントのキリスト者に向けて語っていますが、パウロはコリントにて被った「人の裁きの座」(ベーマ)のことを思い出しながら、本日の言葉を語っているのです。つまり「人を恐れず、神を畏れよ」という事です。私達キリスト者の人生は、私達の命を永遠の命に引き上げて下さった神に対する感謝と共に、神と共に天国を生きる人生です。それは言葉を換えれば「福音にふさわしく生きる」ということです。私達は世にあっては罪にもだえつつ勝利し生き、「裁きの座」は既に「恵みの座」として存在しているのです。