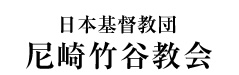「聖 書」
…「わが子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても、力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。」…肉の父はしばらくの間、自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父はわたしたちの益となるように、御自分の神聖にあずからせる目的でわたしたちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた実を結ばせるのです。
だから、萎えた手と弱くなったひざをまっすぐにしなさい。また、足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろいやされるように、自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。
(ヘブライ人への手紙 12章5~13節)
説 教 「子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである」
私共は「小さな者」です。しかし天国を持っています。この天国の恵みは主の「十字架の贖い」を通して、主より与えられたものです。私共の小ささは天国を現すのに大切な特性です。本日の御言葉の最後には、「だから、萎えた手と弱くなったひざをまっすぐにしなさい。」とあります。たとえ主からの「鍛錬」であっても、私共は苦しみに遭い続けるならば「力を落とす」者です。萎えた心になる者です。本日は主から与えられる「鍛錬」を「恩寵の恵み」として受け取ることができるように、御言葉の迫りより、神の「深い愛」を悟る心を与えられましょう。私は先週の説教の中で、小原先生の獄中書簡を紹介致しました。先生は獄中の体験を「神の恩寵」を体験する大学であったと告白されました。皆様は、小原先生が信仰の巨人であったので、「特別な人」と思われるでしょう。しかし私は違う感想を持つのです。先生は苦労の人であり、「小ささ」を生きた人であったと思っているのです。先生は小さい人であったので、「後の者が先に」なったのだと思います。先日、100周年記念の原稿を畠神父から戴きました。私は、その文章を読む中で胸が熱くなりました。一部分を御紹介します。「救いの歴史を3年周期で読む主日のミサの朗読箇所を始めました。その集まりに西川先生が毎回休まずに出席されましたので、私どもの分かち合いは聖霊の息吹に満たされるようになりました。毎回の交わりは素晴らしく、内なる聖霊の火が灯されるのを毎回感じました。予習のときよりも、より深く聖霊の光に照らされてみことばを聞き、読むことができました。西川先生の祈りの深さと聖書の読みの深さに力づけられました。プロテスタントの先生と一緒に聖書を分かち合える素晴らしい楽しいひと時でした。」私は無任所時代で苦労をしている時でした。今、振り返っても「主からの鍛錬の時」であったと思います。しかし、小原先生が獄中を主を近く感じることができた「恩寵」の場であった語られたように、私も主の鍛錬の時を「恩寵」として受け取っています。私共、弱い者が自分の足で歩む恩寵の道は「轍」となり、私共と同じ弱い者が、信仰の道を踏み外すことなく、「救われ、癒される道」となります。私共は弱い者であり、罪人です。そのような私共を神は「実子」として、「天国を生きる住人」として、懲らしめて(マスティゴー)下さいます。皆様、主の「懲らしめ」を感謝して受けましょう。私共は天国を生きています。最後の審判の時に胸を張って堂々と主の前に出て行くことができる「聖」に与る者です。恩寵の喜びを共に行きましょう。