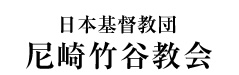「聖 書」
大勢の群集が一緒について来たが、イエスは振り向いて言われた。「もし。だれかがわたしのもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、更に自分の命であろうとも、これを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついて来る者でなければ、だれであれ、わたしの弟子ではありえない。あなたがたのうち、塔を建てようとするとき、造り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰をすえて計算しない者がいるだろうか。そうしないと、土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、『あの人は建て始めたが、完成することはできなかった』と言うだろう。また、どんな王でも、ほかの王と戦いに行こうとするときは、二万の兵を率いて進軍して来る敵を、自分の一万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰をすえて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に使節を送って、和を求めるだろう。だから、同じように、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなたがたのだれ一人としてわたしの弟子ではありえない。」
(ルカによる福音書 14章25~33節)
説教「自分の命であろうとも、これを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない」
先週は「聖霊聖会」御苦労様でした。時間が無く会で語ることができなかったところから本日は解き明かしを致します。殉教者ペトロ岐部神父は、普段にはカスイ岐部と呼ばれていたそうです。一説には「カスイ」は「活水」であったとも言われています。親近感が湧きます。岐部神父は日本にいた頃から殉教者のことを調べていた人でした。それは「同胞愛」によるものです。殉教者の村の人や家族のことなども心配していた人であったので、殉教を覚悟の上で日本に帰り、全国を巡り、キリシタンの人々を励ましながら行脚しました。ついに捕縛され、江戸に送られますが、そこで出会う沢野忠庵(フェレイラ棄教神父)にも信仰に戻るように薦めました。岐部神父はキリストの命を生きた人だったのです。本日の御言葉は「弟子の条件」です。私共は「主イエスの弟子」です。私はイエス様が大好きでしたから、御心に生きたいと常に願っていました。主に喜んでいただきたいと思っていたのです。それは仕事場でも同じで、学校に着くと祈り、「愛し合うことのほか、だれに対しても借りがあってはならない。」(ローマ13:8)と呪文のようにいつも言っていました。しかし御言葉は、呪文ではありません。御言葉は「イエス御自身」です。御言葉に生きたいと願うならば、主イエスに従わなくてはなりません。私にはまだ「自分」がありました。本日の御言葉は文脈で語るならば、「十字架に向かって、まっすぐに進む」主イエスに対して、エルサレムから立ち去るように忠告するファリサイ派の人々が登場するところから始まります。一見親切心に見える物言いですが、十字架の道行を邪魔する悪魔の手先です。その文脈を受けての本日の御言葉です。以前にも申し上げたように「弟子の覚悟」でなく、主が「弟子の条件」を語るものです。主は御自分も「自分の道を進まねばならない」と言われました。私共弟子には、「自分の十字架を背負ってついて来る者でなければ、わたしの弟子ではない。」と言われました。これは「自分の命であろうとも、これを憎まないなら、弟子ではない」と同じ意味です。「憎む」は(ミセオー)で「しりぞける、捨てる」の意です。後で語られる喩も以前に語ったように、「腰をすえて」(カシゾー:座る)が大切な言葉で、「自分の計画」を立ち止まり「捨てる」の意味であると申し上げました。つまり、正しい「神の計画」に生きよの意味です。私共が「御国建設」に生きたいならば、「自分の十字架」(神の計画:私の使命と責任:まっすぐな道)を負うことです。そこに愛が回復され福音が広がり、神の栄光が現れます。